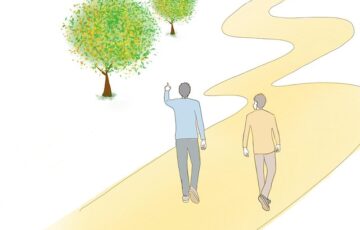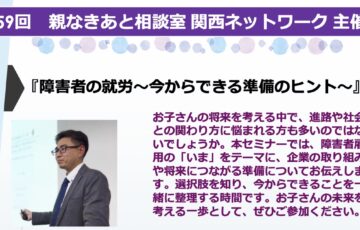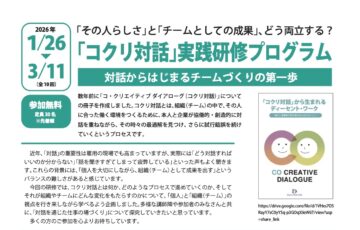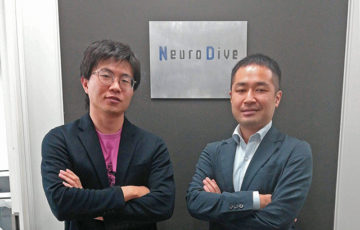障がいは「社会」によって作り出される障壁である
障がい者雇用を考えるうえで欠かせない視点があります。それは「障がいは本人の中にあるのではなく、社会や環境との関わりの中で生じる」という考え方です。いわゆる「社会モデル」です。
例えば、段差があるから車椅子の方が不便になる。段差をなくせば、その障がいは軽減されます。職場においても同じで、理解や環境の整備が不足していると、それが障がいになります。
だからこそ、企業にとっての啓発活動においては、「制度対応」ではなく、「社会モデルを前提に、社会側からできることを考える機会」が重要だと考えています。
「苦手」も「強み」も特性の一部

私は、よく「障がい=できないこと」ではなく「特性」として捉えましょう、と伝えています。
例えば、発達障がいのある方は急な予定変更が苦手でも、決まったルールを守る力に優れています。精神障がいのある方は人間関係に敏感だからこそ、相手に丁寧に寄り添える面もある。
苦手さと強みは表裏一体。学びの場では「できないこと」に目を向けるだけでなく、その裏側にある強みにも気づいてもらうことが大切です。
「何に困っているか?」に目を向け、「対話」しながら、配慮を考えよう
障がい者と共に働く現場からは「どう接すればいいか分からない」という声が多く寄せられます。
そんな時に考えるポイントは、「障がい特性の詳しい知識を得ること」よりも「その人が何に困っているのか」に目を向けることです。障がい特性について詳しい知識はなくても、困りごとが分かれば、具体的な対策や配慮を考えることができます。
(例)
- 口頭での指示が伝わりにくい→指示は口頭だけでなく文字でも残す
- 曖昧な表現が理解しづらい→曖昧な表現を避け、確認の場を設ける
- 優先順位をつけられず戸惑う→役割や困ったときの相談相手を決めておく
併せて、重要なのは対話です。
一方的に配慮を決めるのではなく、障がい者本人と周囲が話し合い、会社として無理のない形を探る。その姿勢こそが大切です。
こうした考え方は、障がい種別や、さらに障がいの有無に関係なく、誰にとっても分かりやすい働き方につながります。
「特別扱い」ではなく「全員に有効な工夫」と理解できたとき、職場の空気は大きく変わります。
仕組みは「誰かの声」から始まる

障がい者雇用のための仕組みづくりは最初から完璧でなくても大丈夫です。多くは、個別のニーズや配慮から始まります。
「体調の波があるので勤務時間を柔軟にできないか」、「体調の波をコントロールしたり、周囲から介入しやすくするために、体調管理ツールを入れられないか」
そんな一人の声をきっかけに制度ができ、やがて他の社員にも役立つ仕組みへと広がっていきます。
ここで忘れてはならないのは、障がい者雇用は“特別な善意”ではなく、会社の成果を高めるための取り組みだということです。配慮や制度は、社員一人ひとりが持つ力を最大限に発揮し、事業に貢献してもらうためにあります。もし「福祉だから」と目的をすり替えてしまえば、不公平感を生んだり、組織全体の成長を阻害する危険さえあります。
だからこそ大切なのは、「私たちは会社の利益をつくるために、一人ひとりが働きやすい仕組みを整えている」という共通認識を持つことです。障がい者雇用は慈善事業ではなく、組織を強くし、成果を高めるための戦略的な一歩なのです。
その一歩をより確かなものにするには、「目的についての共通認識を持つこと」と、「一人ひとりが働きやすくなる仕組みにすること」を両輪として進めることが重要です。
障がい者雇用が組織を強くする
障がい者雇用は法定雇用率を満たすための義務ではありません。取り組む企業を見ていると、職場の多様性が高まり、社員同士の協力や工夫が増えています。結果として生産性や柔軟性が向上することも少なくありません。
障がい者への配慮を通じて「一人ひとりに合わせた働き方」を模索する姿勢は、採用や定着の面でも必ず役立ちます。多様性を尊重する職場は、健常者にとっても魅力的な環境になるからです。
弊社では、そんな環境づくりのサポートをするために社内研修をご提供しています。
私は、研修という理解促進の場を「知識を一方的に伝える時間」だけにしたくありません。研修は「働きやすい職場について一人一人が考える場」です。
もちろん基礎知識は重要ですが、大切なのは、「社員一人一人が働きやすい職場」や「自分たちができること」について考えてみること。
知識以上に、「今、こんなことで悩んでいる」、「こんな時どうするんだろう?」、「今、取り組めることは何だろう?」といった視点をもって参加頂くことで、本当の意味での理促促進につながるのです。
そして、その気づきを少しでも行動につなげていく。それが組織を変える第一歩になります。
終わりに ― みんなのための障がい者雇用

障がい者雇用の取り組みは、特別なことを求める場ではありません。むしろ「社員一人ひとりの働きやすさ」を追求する営みです。その結果として、障がいの有無を問わず力を発揮できる職場が生まれます。
障がい者雇用は「誰かのため」ではなく「みんなのため」。
その気づきを、これからも多くの企業と共有していきたいと思います。