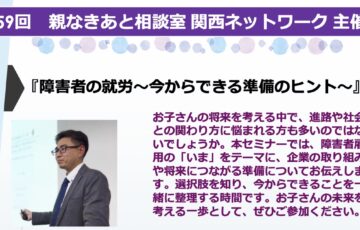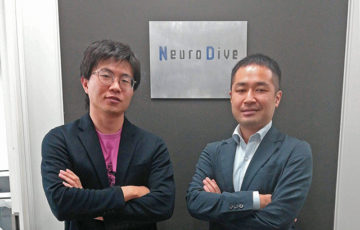ひとり言です。
私の会社である「株式会社日本障害者雇用総合研究所」を設立してもうすぐ丸10年、前職から数えて20年近く「障がい者とはたらく」ということに関わってきました。
改めて自分の役割について考えてみたときに、私の会社では『障がい者の雇用≠企業の負担』を社会に伝えたいと思い、障がい者雇用コンサルティングを通じて「障がい者雇用は企業を成長させる活動である」ことを実践してきました。試行錯誤の連続ではありますが、自分が社会に求められている役割であったり自分ならどのようなことが実現できるかを常に考えてきました。
企業が障がい者雇用に取り組む第一の理由は法定雇用率の達成だと思います。
障がい者雇用の指針のひとつとして明示される法定雇用率の達成は企業にとって目的にしやすい面がある一方で、障がい者のはたらき方や仕事内容よりも、取り敢えず数値が達成されているなら法律では「OK」と考えられやすく、結果として障がい者の視点・意見が汲み取られない雇用事例が一定数存在していると感じています。現在の企業から見た「障がい者雇用」とは、「義務を果たす」「雇用する障がい者は“戦力”<“数値”」と見られているのではないかと考えてしまうことも多く、自分の力不足を痛感するのと同時に悲しい気持ちになります。
仕事柄ですが、当然のことながら障がい者がはたらく場を多く目にします。それは一般就労や福祉就労を含めて、障がいのある人たちが自分が求められている仕事に対して真剣な面持ちで取り組んでいる姿を目にすると心に響くものがあります。最近は職場で勤務する障がい者も障がい特性の多様化が進んできたこともあり、障がいのある方たちを周囲からサポートする支援者を配置する企業が増えてきました。
人によって容姿や性格に違いあるのと同様に障がい由来の特性、得意・不得意、求める配慮などは千差万別と表現できるほど様々です。はたらく障がい者の中には支援者からのサポートにより仕事で求められるパフォーマンスを出すことができることを考えると支援者の役割は重要な立場といえます。
企業や福祉就労で障がいのある方たちをサポートする支援者から「利用者の成長」「配慮について」など、日常の業務に関連した相談や悩みを聞くことも少なくありません。自分が仕事をさばくのとは違って障がいのある人が仕事で成果を上げるためにサポートをする支援者の役割は特有の難しさがあります。私自身も改めて支援者の役割について考えてみました。

障がい者就労継続支援A型事業所・B型事業所を例にしてみたときに、支援者の役割として複数挙げられる中で重要だと思うのが利用者である障がい者が目指す姿や状態になるための「支援の提供」だと思います。「自立を目指す人」「就職したい人」「日中活動として社会と繋がりたい人」などなど。就労支援サービスを提供する事業所には、概ねこういったことを希望している利用者が多く通われていると思います。理想としては全ての希望が叶えられると良いのですが、実際のところは様々な理由により実現の可否も変わってきます。とはいえ可能な限り個々が希望す姿に近づくための努力を利用者が積み重ねることができるように、事業所並びに支援スタッフが本人を支えること(=配慮)が重要だと思います。
しかし、利用者が仕事を行う中、支えることに比重が偏り過ぎてしまっている一部の事業所では、本来の目的である「利用者の希望する姿を目指す」が置き去りになっているように感じられます。事業所では利用者の日中活動として企業などから請け負った仕事に従事させているところが多くあります。利用者はそれらの仕事に従事することで「就労訓練を積む」「自分の得意・不得意を認識」「社会活動に参加」といった経験を通じて成長、自立を目指します。
一方で仕事への従事が主たる目的になってしまうと、「納期に間に合わせる」「1日のノルマをこなす」ところにばかり意識が向いてしまい、利用者が望む成長・自立に向かって進むことが遠ざかってしまいます。
本来の「利用者が成長する」「できることが増える」「得意を伸ばす」に対して意識が向けられていると、普段から関わっている支援者はそれらを実行するための配慮や工夫を日常的に取り入れる考え方が備わります。結果として「利用者が成長する」「できることが増える」「得意を伸ばす」が実践されることで、「納期に間に合わせる」「1日のノルマをこなす」ことができるようになると考えます。
繰り返しになりますが、支援者の求められる役割は利用者が希望する姿になることを忘れず、「利用者が成長する」「できることが増える」「得意を伸ばす」ことができるような配慮と工夫を重ねることを継続することです。
企業の支援者も求められる役割は同じだと思います。仕事とのバランスを図ることは大変難しいことではありますが、配慮と工夫を重ね続ける先で得られる仕事で障がい者の成長した姿を一緒に喜ぶのは何ものにも変え難い経験のひとつだと感じます。