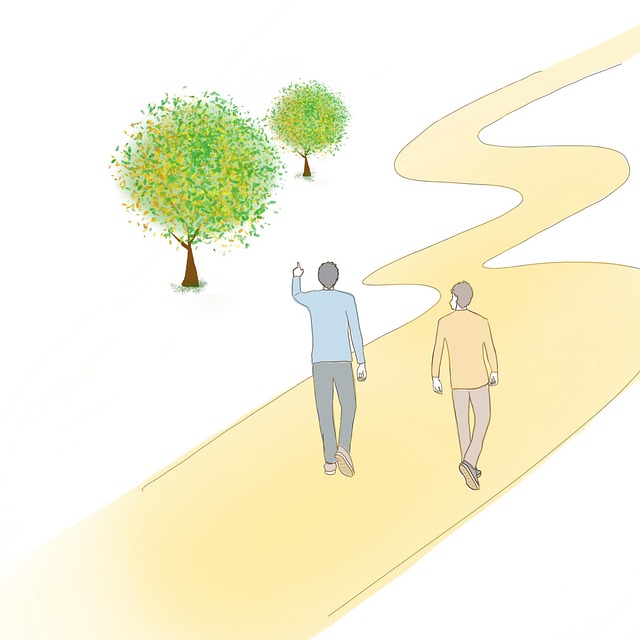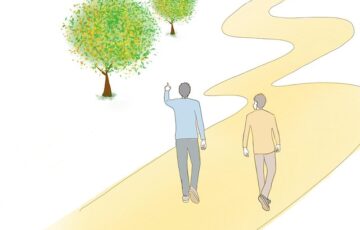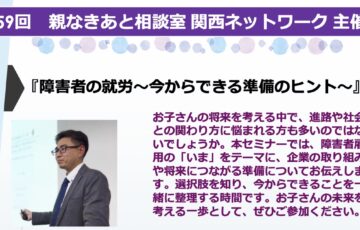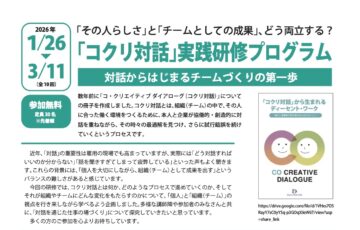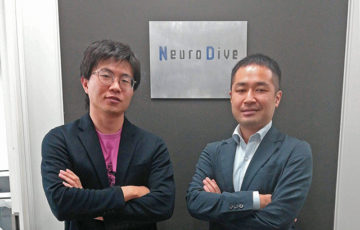私たちは今、障がいのある学生など、「働きづらさを抱えた大学生」の就労支援に取り組んでいます。
けれど、最初から大学生に注目していたわけではありません。最初は、すでに社会に出てつまずいた人たちと向き合う就労移行支援の現場で、離職をされた障がいのある方にかかわることがありました。
あるとき、思ったんです。「もしこの方々に、もう少し早い段階でサポートができていたら、違う未来があったのではないか」と。
その気づきが、大学生を対象にしたインターンシップを始めるきっかけでした。企業でうまくいかずに戻ってくる人たち。社会で“失敗”した後にやっと支援の選択肢がある。それでは遅すぎる。そう強く思うようになりました。
もうひとつ、今でも忘れられない出来事があります。ある発達障がいのある元・専門職の方と出会ったことです。彼は、仕事で必要とされるコミュニケーションが苦手でした。結局、その仕事は難しく、最終的に離職しました。しかし社会には、彼が改めて活躍できる選択肢がほとんどなかった。興味があったITの分野に進む道も、その当時の就労支援では提示されなかったんです。
「向いていない仕事でもやっていかないと、自分は社会の中に居場所がないですから」
——彼が口にした言葉が、今でも心に残っています。

私は、こうした人たちが“社会に出る前”に伴走できる場を作りたかった。それが障がいのある大学生向けインターンの立ち上げにつながりました。
インターン開始当初は、企業に「発達障がいの学生を受け入れてください」とストレートに伝えても、なかなか理解が得られませんでした。そこで私は伝え方を工夫しました。「コミュニケーションが苦手で、自信が持てず、一歩踏み出せずにいる学生がいます。社長の力で、社会への一歩を後押ししてくれませんか」と。すると、多くの企業が「それならやってみよう」と言ってくれたのです。
この“言葉の届け方”の違いが、社会との距離を縮めることになると知りました。
けれど、インターンに参加したからといって、すぐに就職につながるわけではありません。だから私たちは、「戻ってこられる場所」として、就労移行支援事業所も立ち上げました。そこには“第二の母校”というメッセージを使ってきました。学校にいい思い出がない、疎外感を感じてきた学生にとって、愛着を持てる新しい場所になってほしい。そんな願いがあります。
やがて就労移行支援を運営していく中で、発達障がいやコミュニケーションが苦手な若者に限らず、手帳や診断がない「グレーゾーン」の方々への支援も重要だと感じるようになりました。そうした人たちにも届くサービスをと考え、インターンシップ事業から「働く力プロジェクト」へと拡張していきました。

また当時、社内のビジョンも「発達障がいのある人が活き活きと働ける社会」から、「働きづらさを抱えるすべての人が活き活きと働ける社会へ」と言葉を見直しました。発達障がいという枠だけでなく、もっと幅広い人たちを対象としたいという思いがそこにはあります。
そして2020年、コロナ禍が社会を変えました。合同説明会も中止になり、「このままでは学生が企業と出会えなくなる」と危機感を持ちました。そこから生まれたのが、オンライン就活イベント「家でも就活オンライン」です。Zoomでの開催、学生と教職員の参加、今では当たり前となった仕組みが、そこから広がっていきました。
私は「社会側が変わらなければ、どれだけ本人が努力しても報われない」と思っています。だからこそ、企業に向けたコンサルティングや研修にも力を入れてきました。1社が障がいのある方を10人受け入れる風土と仕組みができれば、5社で50人、10社で100人の居場所ができます。さらにその次の広がりも生まれるでしょう。そのような社会側の変化の後押しをするのも、私の役割の一つだと思っています。
今、私が大切にしていることがあります。現場の一人一人のスタッフが、共通のビジョンの元、それぞれの考えを持って動いてほしいと思っていることです。それにより、困難があっても乗り越えられるし、自分の仕事に「自分ごと」として責任が持てると思うからです。
私たちが掲げているビジョンは、「働きづらさを抱えた人たちが、生き生きと働ける社会をつくること」。それはつまり、「自分の強みが発揮され、ちゃんと評価されること」。そして「やりたいと思えることがあり、安心して選べること」。そんな“生き生き”が一人でも多くの人に届けられるよう、これからも取り組みを続けていきたいと思っています。
URL:https://en-c.jp/com/?ml
家でも就活オンライン
URL:https://career.en-booster.jp/ids/?ml