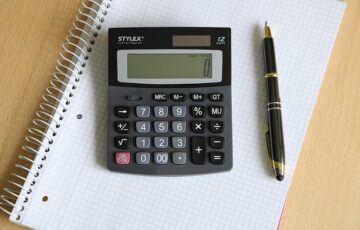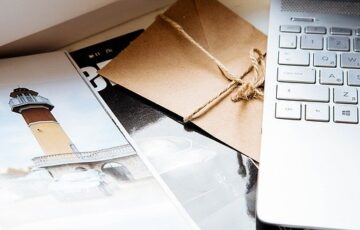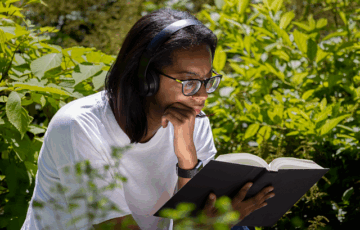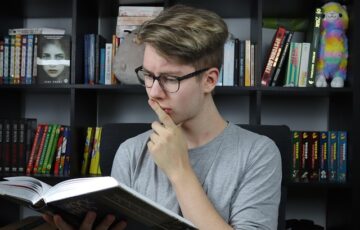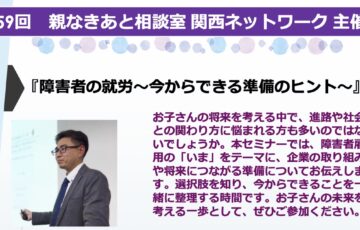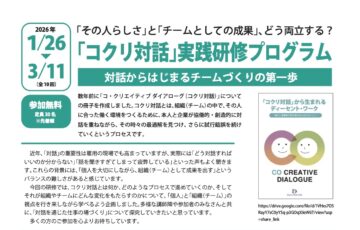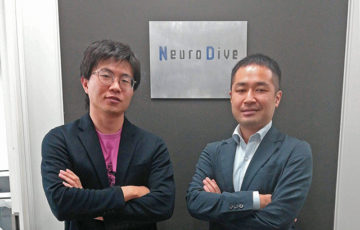ひとり言です。
2025年も年の瀬に差し掛かり、街並みも綺麗なLED照明が飾られるなど少しずつ年末らしい雰囲気が感じられる時期になりました。毎年12月なると厚生労働省から企業の障がい者雇用に関する統計「障害者雇用状況の集計結果」が公表されます。
企業は管轄の労働局に自社の障がい者の雇用状況を報告(六一報告)します。この報告された内容は都道府県の労働局から厚生労働省に集約されます。全国にある企業における障がい者の雇用数や法定雇用率の達成割合はどうだったのかなど、項目ごとに出された統計値を見ることができます。
直近の令和6年のそれを見ると企業による障がい者の雇用数は677,461.5人でした。これは法定雇用率が定められてから最も多い値となりました。内訳は、
- 身体障がい者の雇用数:368,949.0人
- 知的障がい者の雇用数:157,795.5人
- 精神障がい者の雇用数:150,717.0人
となり、雇用数の中で最も多い特性は身体障がい者になります。
最近は精神障がい者の雇用数が年々増加していて、令和7年には知的障がい者の雇用数を抜いて2番目に多くなるだろうと予想します。また、障がい者の雇用数が初めて700,000万人を超えるのではないかと思います。これは、企業による法令を遵守するという姿勢、更に多様性が活躍する社会の実現やCSV経営(Creating Shared Value(共有価値の創造))といった社会課題に対する考えが進んできたことが大きな要因のひとつだと考えます。
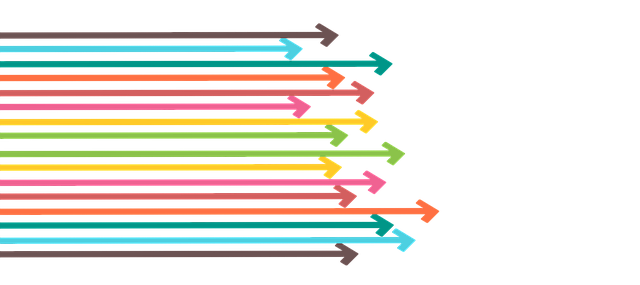
我々がよく目にする情報はこれらになるのですが、実際に企業で雇用されている障がい者の数がもっと多いということをご存知でしょうか。「障害者雇用状況の集計結果」とは別に厚生労働省が5年ごとに実施している「障がい者雇用実態調査」と言われる調査があります。
実施の目的としては、
- 「事業所の調査」
企業が障がい者を雇用する際の雇用管理(配置、職務内容、賃金、労働時間、福利厚生など)に関する取り組みの現状や課題を調査する。
- 「個人(障がい者)の調査」
雇用されている障がい者本人の仕事内容、労働時間、賃金、通勤状況、生活の状況、障がいに関する配慮事項などを把握する。
- 「政策立案への反映」
これらの調査結果を分析し、障がい者雇用促進のための新たな施策の検討や、既存の支援制度(助成金制度の充実、外部支援機関との連携など)の見直し・充実に役立てる。
が挙げられます。
「障害者雇用実態調査」が「障害者雇用状況の集計結果」と違うところを挙げると、
- 雇用義務のない従業員規模5人以上の企業を対象に調査を実施
- 公表されている数値はあくまでも推計による
- 全国にある企業から無作為に抽出した約 9,400事業所が対象(回答は6,406 事業所)
- 雇用数以外にも雇用条件や生活状況、職場での配慮など実態の把握ができる
になります。
「障害者雇用実態調査」による全国の障がい者雇用数の推計では1,107,000人が企業で働いている事になります。内訳は
- 身体障がい者の雇用数:526,000.0人
- 知的障がい者の雇用数:275,000.0人
- 精神障がい者の雇用数:215,000.0人
- 発達障がい者の雇用数:91,000.0人
です。
あくまでも推計になりますが、障がい者雇用義務のない従業員数5〜43.5名未満の企業(※調査のあった2023年は法定雇用率2.3%だったので雇用義務企業は従業員数43.5名以上)には約30万人以上の障がい者が雇用されていることになります。

では、なぜ障がい者の雇用義務のない企業が障がいのある人材を雇用しているのかという疑問が浮かび上がります。大きな理由としては「障がい者も十分な労働力である」ということです。少子高齢化が進んでいる日本の国内企業にとって、労働力の確保は事業継続において大きな課題のひとつとなっています。特に従業員規模の小さな企業にとってはより深刻な状況となっています。
東京商工リサーチ「「後継者不在」年々上昇し62.60%に 代表者が高齢の企業ほど、上昇が顕著」
URL:https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1201982_1527.html
過去に取材を通じて、障がい者の雇用義務がないにも関わらず障がい者を雇用する企業のお話を聞かせていただきましたが、最も多いと感じたのは「労働力としての障がい者雇用」でした。
障がいがあっても採用する側の企業による工夫や考え方の転換によって、足りない労働力を補うことができるということに気が付いている経営者や人事担当者は“流石だ!”と思います。実践している企業にとって就職を目指す障がい者界隈はブルーオーシャンに見えているかもしれません。
もちろん、これまで障がい者を雇用したことがない企業にとっては簡単に進められないところもあります。しかし、労働力の確保ができないままの状態を放置し、損害を増すばかりなのであれば、方針転換をするだけの価値は十分にあると考えます。ひとりの障がい者を雇用することで、それ以降は他社に比べて労働力の確保に困ることが格段に減少させられるでしょう。
結果論ですが、障がい者が活躍できる組織は人材を選ばずに活用することができると思います。その先には収益だけではない社会的な立場の成長を叶えることができると思います。また、小規模の企業であれば、従業員ひとりひとりに目が行き届くので、従業員の声を反映した組織づくりが実現させやすいと感じます。
おそらく、障がい者雇用を実践している企業の経営者はそのことにいち早く気が付いたのではないでしょうか。