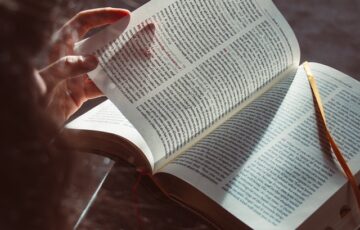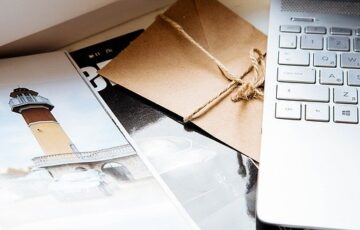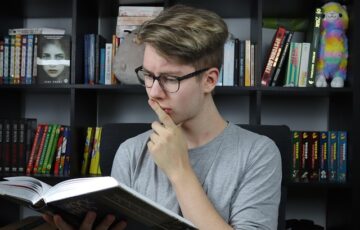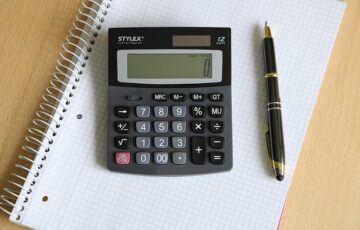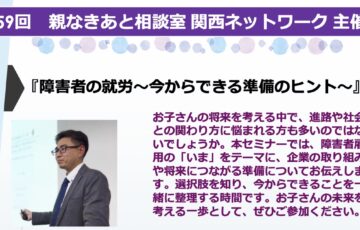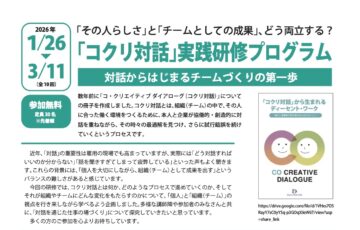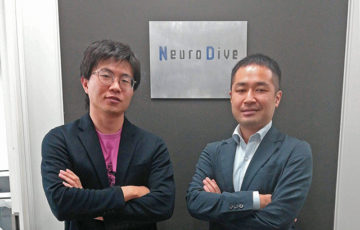ひとり言です。
先日、障がい者就労に関する「闇」をテーマにした動画を見ました。
URL:https://www.youtube.com/watch?v=7X8OsEvmsk8
【ひろゆきvs障害者就労】障がい者雇用率制度…企業が抱える問題・障害者の一般就労は可能なのか…?【ReHacQ高橋弘樹】
URL:https://www.youtube.com/watch?v=FJr0_AXDDQw
2回に分かれていますが、合わせて1本の動画になっています。動画で取り上げられているテーマを活字にすると「重たい!」といった印象を受けますが、前半は「障がい者就労支援福祉の現状」について。後半は「障がい者の雇用に見られる問題点」にスポットを当てた内容となっています。
パネラーは、
- 竹村利道氏(日本財団 公益事業部 シニアオフィサー)
- 白石圭太郎氏(社会福祉法人チャレンジドらいふ 理事長)
- 中島隆信氏(慶應義塾大学 商学部 教授)
の3名で、皆さん障がい者就労の分野では高い見識のある方々です。また3名とも違う立場としてこの討論の場に参加されていますので、それぞれの視点からの意見を聞くことができるため、非常に満足度が高いと感じました。
ネタバレになりますので詳細な内容は控えますが、自立や就労を目指していたり、すでに働いている障がいのある方々が置かれている環境下で実際に起こっている課題や問題点について詳しく語られています。この動画内で語られている内容は、仮に自分が障がい者を雇用する企業の人事担当者であったなら、決して対岸の火事ではなく、いずれ採用や人材の確保、障がい者の戦力化といった領域にも大きく関わってくることだということが分かります。
◆障がい者就労継続支援A型事業・B型事業に関する「闇」
障がい者を対象とした福祉サービスの中で“就労”を主とした目的としている事業は以下の5つが挙げられます。
| サービス名(正式) | 対象者 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 就労選択支援 |
働き方に迷っている人 |
希望・能力の評価、サービス選びの相談 |
2025年10月開始、B型利用前は原則必須 |
| 就労移行支援 |
一般企業で働きたい人 |
面接練習、履歴書作成、職場実習 |
企業就職を目指す準備 |
| 就労継続支援A型 |
雇用契約で働けるが企業は難しい人 |
事業所と雇用契約、最低賃金以上の給与 |
安定した仕事場を提供 |
| 就労継続支援B型 |
雇用契約は難しいが作業したい人 |
工賃を受けて作業、生活リズムを整える |
社会参加のきっかけになる |
| 就労定着支援 |
就職後に職場に定着したい人 |
生活相談、職場調整、トラブル対応 |
就職後のフォローアップ |
障がいのある方は、その障がい由来からくる特性・心身の状態・置かれた環境等を踏まえながら、一般企業への就職が目指せる人から自立や就職を実現させる際に求められる知識や自己理解、または社会生活の方法を身につける段階の方まで、様々な状況にあります。ひとりひとりの状況に応じた就労に関する福祉サービスが上記の一覧となります。
このうちA型とB型の違いが分かりにくいと感じられている方が多いと思います。
この動画でも進行役の方が障がい者の就労分野の知識が浅いため、パネラーの皆さんから説明を受けながら少しずつ理解する場面を見て「多くの方がこの2つの事業の違いって何?感じるよな。」ということに気づきました。大きな違いのひとつとして「最低賃金の保証」が挙げられます。
A型では利用者(施設に通う障がい者のこと)は事業所との間で雇用契約を締結し、福祉サービスによる支援を受けながら労働者として働きますので、最低賃金の保証を受ける形になります。
一方のB型では福祉サービスの提供を受けながら作業を行いますが、利用者と事業所の間では雇用契約は結ばれませんので最低賃金の保証もありませんから、それよりも低い工賃(返金して時給200円にも満たない額)として報酬を受け取っています。
多くの人は「なぜB型に通っている障がい者はA型に通わないの?」という疑問が浮かんできます。
この動画でもそういった場面が見られました。他にも昨年以降、A型事業所の閉鎖が相次ぎ発生した結果、解雇された障がい者にその皺寄せがいくといったニュースが世間を騒がせることになりました。原因のひとつは事業所を運営する際に基本となる制度における設計に間違いがあるという指摘があります。詳しい解説がこの動画で拝聴することができますが、この問題を解決させるだけの意見が見出せないところに事業所と障がい者が置かれている状況の複雑さを感じさせられます。また、障がい者を支援する福祉が障がい者から搾取するとはどういうことなのか。というテーマは非常に興味深い内容になっていて気持ちがモヤモヤとさせられます。
◆障がい者の雇用を進める社会が生んだ「闇」
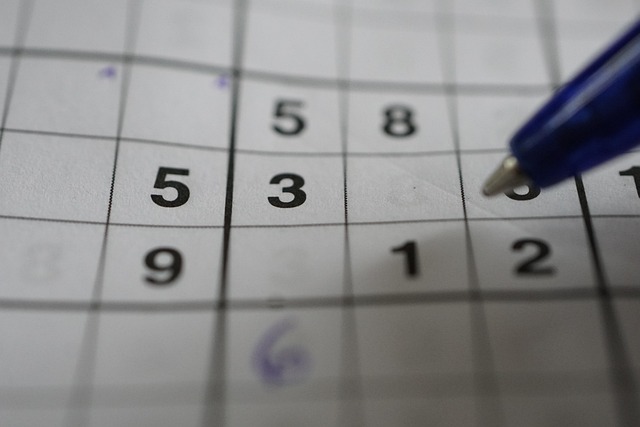
法定雇用率が2024年4月に2.5%へ引き上げられ、続いて2026年7月には2.7%となります。これらの法律改正に合わせて、企業の障がい者雇用実数も毎年右肩上がりに増加しています。法律の遵守や多様性、活躍を実現させる組織づくりなど、社会的課題の解消につながる取り組みを求める機運の高まりから、障がい者の採用を進める企業による求人が増えています。
一方で採用した障がいのある人材にはほとんど仕事を与えず席に座っているだけ給与を支払っている企業が散見されます。また、雇用した障がい者を自社とは違うところに出社してもらい本業と関連性のない仕事をしてもらう“障がい者雇用のアウトソース”と言われるビジネスがあります。皮肉なことに、法定雇用率の引き上げと共にこれら“障がい者雇用のアウトソース”を提供する企業の売上が過去最高になったと聞きます。いわゆる「障がい者雇用が数合わせ」になっているひとつの姿だと言えます。
本来であれば、法定雇用率の引き上げにより、障がい者の自立につながるであろう企業への「就職」のはずが、一部の雇用の現場では数合わせのための雇用となっています。働くことを望んで就職した障がい者は経済的活動に参加させてもらえず、企業の一員としての立場も保証されていない状況があります。なぜこのような状況が生まれたのかということを動画内ではわかりやすく説明がされていました。また、メインコメンテーターのひろゆき氏(2ちゃんねる開設者)はそのキャラクターの通り、辛辣な表現を用いていますが、現在の障がい者雇用における課題を見事についたコメントを発している姿は清々しさを感じました。