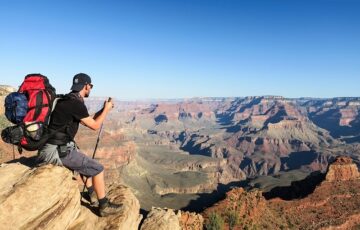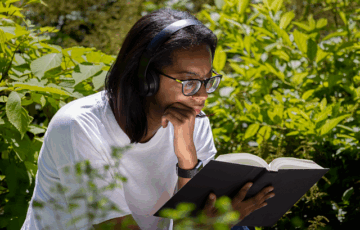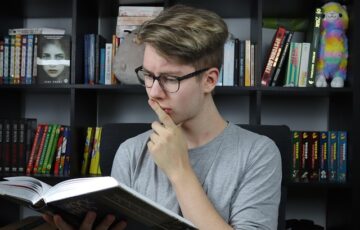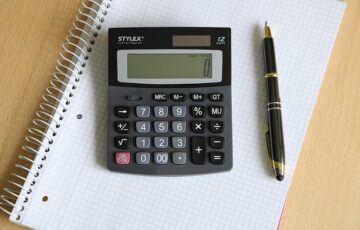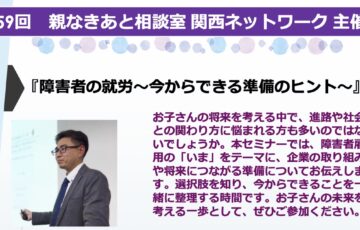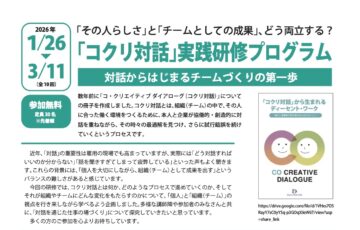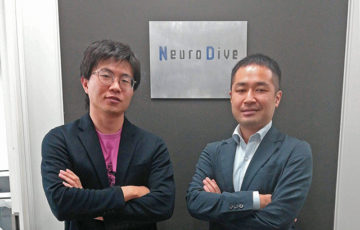前回からの続き
採用後のミスマッチは極力避けたいと考えます。業務との適正、人間関係、受け入れ環境・体制、障がいへの理解不足、文化の違いといったことが理由によるミスマッチは、早い段階での取り組みにより改善させることができます。組織内への研修や障がい者実習の受け入れなど、障がい者に関する理解や知識の習得を目指す方法を導入することで実現させることができます。
また、採用プロセスでも判断基準を明確にすることで一定水準の人材確保に繋げることができます。加えて自社が求める人材像についても明確に伝えることで、雇用してからの「違うかった」を減らすことができます。人事担当者の立場であれば、せっかく集めたエントリーを失う怖さもありますが、求める人材像とのギャップを抱えながらの雇用はいずれ顕在化するミスマッチが起こった時の苦労を先送りしていることになるので、早い段階で求めている人材かどうかの判断をしておく方がいいと思います。
障がい者雇用が雇用率達成を目的とした単なる取り組みとする枠を超えることで結果的には「求めている人材の獲得」「期待以上の業務成果」「企業の成長」へとつながる活動にすることができます。一般的に企業が採用したい人材と同じことを障がい者にも求めていいのです。
「自社では単なる労働力ではなく、仕事を通じて成長したい人材が欲しいのです」と。

これからは地方在住の障がい者の採用がもっと進んでくると感じています。
地方の企業が地域に暮らしている障がい者の採用はもちろん、都心部にある企業が離れた地域に暮らす障がい者を在宅ワークとして雇用するケースです。すでに一部の大手企業では在宅ワークによる障がい者の雇用枠を広げ、定着までの実績を上げるところが増えてきました。地方に目を向けてみると、仮に都心に近いところで生活をされていたなら、いくつかの企業にエントリーをすることができたであろう人材が一定の割合でいらっしゃいます。
実際に在宅ワークにより障がい者の雇用を実践している企業が重要だと考えて配慮する取り組みのひとつとして挙げられるのは「孤立・孤独感」をどのようにして排除するかという点です。
ITの発展、多様なコミュニケーションツールにより人と人のつながるスタイルも大きく変化してきました。そういったツールの活用で遠くに離れた人とも意思伝達ができるようになった一方で頼りすぎてしまったことで、相手の顔が見えにくくなり、汲み取るべきところを見逃してしまうことは避けたいと感じます。在宅ワークだからこそ人との関係性を重視したコミュニケーションの図り方に目を向けることで「孤立・孤独感」を遠ざけることができると考えます。定期的な1on1でも形式的なものではなく、普段の様子との変化や相談できる雰囲気を作りつつ、業務で期待している気持ちを伝えることも大切だと思います。
障がい者雇用が在宅ワークにより地方に在住する障がい者への広がりが進むことに伴って、障がい者就労支援機関の役割も変化すると考えています。ここでは就労支援機関として就労移行支援事業所(以後、移行支援)と就労継続支援B型事業所(以後、B型)について考えてみたいと思います。就労支援機関の求められている役割には地域性との密接な関係があると感じています。
例えば都心部にある就労支援機関を見ると、就労移行は利用者の就職が大きな目的のひとつでもあり、企業にとっても採用ルートのひとつとして確立されつつあることから、企業と接点が持ちやすい特徴があります。また、雇用後の定着についても対応するケースが多いため、就職先とは長い付き合いになることが少なくありません。続いてB型を見てみると、就職が困難だと言われる障がい者が日中活動のひとつとして利用する機会が多いこともあり企業との接点は薄いと感じます。
それは、企業側からB型を見たときに一部の事業所を除いて、採用ルートとしての役割からは距離があると感じられており、どちらかといえば、内職系の作業をお願いする障がい者施設といった捉え方が多くあることもその理由のひとつです。

一方で都心部以外の就労支援機関に目を向けると違った景色が見えてきます。
地域によりますが、就労移行は数が非常に少なく、理由は開設しても障がい者の採用を進める企業が少ないため2年以内の就職が困難な状況となり、結果として事業所を閉鎖したりB型に事業転換しているからです。B型に関しては日中活動のひとつである役割は同様ですが、都心部であれば企業の求人にエントリーして就職ができそうな人材が近隣に就労移行がないためにB型に通所しているケースが見られ、一定数の労働力を持っているB型が少なくない印象です。
地方では労働力の確保が困難なケースがあるため、B型の労働力を活用する企業が少なくなく、施設外就労により労働力を確保しつつ適正の合う人材は直接雇用のルートを確立している企業もあります。

今後は都心部にある企業がリモート雇用を通じて地方在住の障がい者を在宅ワークとしての採用が今よりも進むであろうと仮定した時にB型から企業への就職ルートが今よりも進むと考えます。地方のB型は在宅ワークによる雇用を対象とした定着事業の取得、企業担当者との連絡・報告や本人へのケア、万が一の状況発生時の対応・体制づくりなど企業の採用ニーズに対応することが求められるようになります。裏を返すとこれら求められる対応が可能なB型は企業にとって重宝にされると思います。
そもそも、なぜB型なのかといえば、全国にある就労支援事業所の中で事業所数が一番多い支援機関がB型だからです。(就労移行支援事業所「3,301ヶ所」、就労継続支援A型事業所「4,676ヶ所」、就労継続支援B型事業所「16,713ヶ所」、就労定着支援事業所「1,809ヶ所」)
今後、障がい者雇用が進むにつれ、支援機関が求められることについても変化が生まれます。