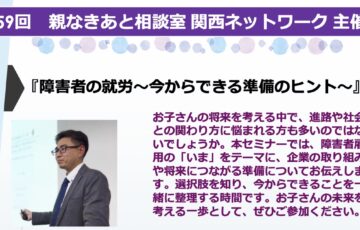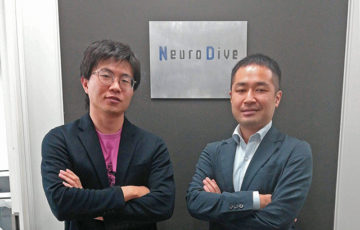今回は先日鑑賞した映画『みんなの学校』についてお話をしたいと思います。
全校生徒の10%超が何らかの支援を必要としている生徒が通う小学校が大阪市にあります。その学校は公立で2006年に設立された新しい学校なのですが、生徒たちは先生や職員はもちろん、保護者に地域住民からの協力・支援を受けながら学校生活をおくっており、不登校児が1人もいないそうです。
映画を鑑賞する少し前に障害者雇用に力を入れておられるある企業の担当者からこの学校「大阪市立大空小学校」のことを聞きました。インターネットで調べるとたくさんの情報が出ており、有名な学校なのだと感じました。
数年前にテレビ局が大空小学校の取組みを取り上げ、ドキュメンタリー映画として製作されてとのことです。是非観たいなぁと思っていたところ、偶然にもお話を聞いた2週間後に自宅近くの区民センターで無料上映会があるということを聞き、当日は他の予定を入れず映画の鑑賞をメインにしました。
会場はたくさんの方で席が埋まり、特にお子さんを連れたお父さんやお母さんの姿が多い様に感じました。上映時間は1時間30分ほどの長さですが、集中して鑑賞することができる構成となっていました。
ネタバレになりますので映画の詳細には触れませんが、「支援の必要な生徒」を中心に「同級生」「先生や職員(先生同様に登校しない生徒の家に迎えに行ってました)」「保護者」「地域住民」がどのように関わっているのかがしっかりと伝わる内容でした。
この映画に出てくる「支援の必要な生徒」とは必ずしも障がいを持っているということではなく、家庭環境が原因で生活リズムが乱れて朝起きることができなかったり、授業で必要なモノを買ってもらえなかったりなど、色々な問題を抱えた子供たちも含まれています。
ところで映画を観ていて気を引いたことがありました。「同級生」たちです。「支援の必要な生徒」の動向や個々に必要な支援も気になる点だったのですが、なによりその子たちと一番近い存在となる「同級生」たちの関わり方に心を持っていかれてしまいました。授業中に学校を飛び出したり、教室に入らなかったりということが発生すると、先生ではなく「同級生」が声を掛け、手を繋いで席に連れていくという行動を特別なことではない様子で行っていました。
この「特別なことではない」ということが非常に重要な意味を持っているのです。
『企業で働く人たちは何故障がい者と一緒に働くことに抵抗を感じるのでしょうか。』
このことについて持論があり、セミナーや講演時にお話をしているのですが、“障がい者と接する機会が少ないため理解が出来ていない”ということです。
身内や近しい存在として障がい者のいない多くの人は、障がいを持つ人と初めて接するのは小学生の頃ではないでしょうか。学年に1~2名ほどの障がいを持つ同級生がいて、ホームルームや体調がいい時には一般学級の席に座っていたり、それ以外では特別支援学級(私が小学生の時は養護学級と言われていました)で過ごしたりしています。でも、中学生や高校生の頃になると障がいを持つ同級生は学力や体力面の違いなどから一般の生徒たちとは離れた関係性へと変わっていきます。この多感な時期に。
その次に障がい者の人たちと一緒になるのが職場となります。これってかなり無理があるように思うのは私だけでしょうか。お互いを理解しあう時期に距離を開けられ、その後社会という場面でいきなり共存を強いられてしまうと当然のことながら拒否反応が生まれるのは理解できることだと思います。
私が企業から障害者雇用に関するご相談をいただいたときに最初に取り掛かる部分は周囲の障がい者理解という点です。
これは、障がい者の雇用を上手く進めるためには従業員の理解と協力が必要不可欠となります。従業員に対して無理矢理に障害者雇用の取組みを押し付けたり、理解を得ないままスタートさせるのではなく、企業が障害者雇用に取組む理由と障がい者に関する正しい理解を持ってもらうところが必要となるからです。
足に障がいを持つ人が建物の上階へ行く際にエレベーターを使用することでその瞬間だけ“障がい者”ではなくなります。これはエレベーターが障がいのある部分の働きを補うからです。
同じように障がい者の障がいのある部分や特性をツールに頼ったサポートだけではなく、周囲の理解ある配慮により障がいが障がいでなくなる場面が出てくるのです。

この『みんなの学校』に出てくる「支援の必要な生徒」たちはみな個性があり、「同級生」をはじめ「先生」たちなどの周囲は大変に感じる時もあるだろうと思います。
同じように「支援の必要な生徒」たちも生きにくい今を大変に感じているから問題ある行動に出るのだと思います。
学校と会社とを同じフィールドとして比べることはできません。でも、この学校での取組みから学ぶことはできます。改めて障がいを持つ人たちとの関わり方を考えるきっかけとなる映画でした。