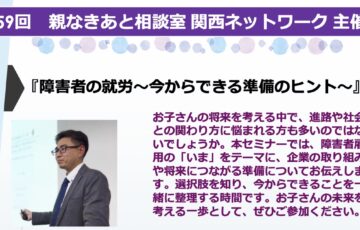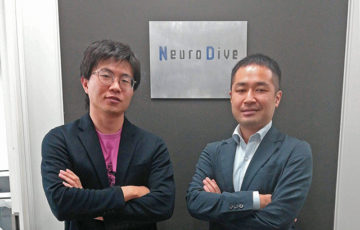今回ミルマガジンでは、株式会社リコーの障がい者雇用事例をご紹介いたします。
皆さんもよくご存知の同社は1936年に設立され、現在はデジタルサービス、印刷および画像ソリューションなどを世界約200の国と地域で提供しているグローバルカンパニーです。事業を通した社会課題解決と並行して、事業領域内外に関わらず、“意志と責任”をもって重点的に取り組むことを決めた社会貢献活動のひとつに「若者向けデジタル支援プログラム」があります。このプログラムでは障がい者手帳の有無に関係なく、急速なデジタル社会の進展のなかで、情報格差により就労に困難を抱える若者を対象に、NPO法人と協働でリコーのリソースを活用した就労支援を実施。参加者が自分のやりたいことや強みを活かした進路を見つけるための支援活動を行っています。
同社の障がい者雇用に目を向けると、多様な障がい特性の障がい者雇用を実践しており、発達障がい者の雇用においては2015年より技術職での採用を開始。現在10名の発達障がい者がリコーグループ全体に在籍し、離職率は0%となっています。
その中のひとりである永田氏は2022年9月に発売されたリコー独自の技術を取り入れたカラーマネジメントソリューション「RICOH Auto Color Adjuster(リコーオートカラーアジャスター)」のアルゴリズムの開発者のひとりとして同社に大きく貢献し、職場だけでなくリコーにとってなくてはならない存在となりました。発達障がい特性のひとつ「ASD」がある永田氏が開発部門でどのように受け入れられ、そして強みを発揮し、周囲から必要とされる存在になったのでしょうか。
取材では同社プロフェッショナルサービス部 人事総務センター 人事サポート室 採用グループ グループリーダー 安積正哉氏、同採用グループ 中村万里子氏、永田氏の職場で一緒に勤務されているデジタル戦略部 デジタル技術開発センター 第2開発室プリンティングDX開発グループ 種子田裕介氏からお話をお聞きしました。

永田氏を採用された背景とプロセス
《話・安積氏、中村氏、種子田氏》
当社では経営戦略のひとつとして「ダイバーシティ&インクルージョン」と「ワークライフ・マネジメント」を掲げています。「ダイバーシティ&インクルージョン」とは、『多様な人材が個性・能力を最大限に発揮することで イノベーションを生み出し、価値創造につながっている。』と考えます。また「ワークライフ・マネジメント」では、『効率的な働き方で仕事と生活の双方の充実が実現し、 さらに質の高い成果を生むサイクルを創っている。』と考えています。
従業員一人ひとりのやりがいと活躍の実現がリコーの企業価値の向上につながるからです。特に「ワークライフ・マネジメント」は、よく耳にする言葉であれば「ワークライフ・バランス」となるのですが、それぞれを天秤のようにバランスを取るというよりも、当社では仕事と生活の両方が大事であるとの考えから、自身でどちらも質の向上を追求していく行動が求められます。
この考え方をもとに多様な人材が活躍できる職場環境を構築する中、障がい者の雇用についても個性・能力を最大限に発揮し、力を融合することで、新しい価値創造のための変革を加速する「変革の当事者」を求めています。障がいのある社員であっても、自ら考え、行動できる、職場にとって必要な人材として成長することを期待しています。そのため、障がい者も活躍できる職域拡大を目指すひとつとして、発達障がい者の雇用を2015年に開始し、現在は技術職6名、事務職4名の計10名の発達障がい者が勤務しています。
そのおひとりである永田氏との出会いは、永田氏の通っていた大学で彼の支援者から当社を紹介いただいたのがきっかけでした。選考としては、一般応募者と同じ基準による適性検査の後に自身の障がい特性を説明するナビゲーションブックの共有をお願いし、履歴書と合わせて書類選考を実施しました。その後に電話による配慮事項の聞き取りと確認、人事部にて面談を行います。
人事部による面談の合格者は配属予定の部門による面談へ進みます。配属先の選定に当たっては、発達障がい者の受け入れに積極的な姿勢のある研究開発部門を候補のひとつとして考えていました。永田氏とその部門のマネジャーの面談では、面談者からの質問に対して永田氏はなかなか回答できない場面もあり、面談者が「雇用は難しいのでは」と感じてしまうほどでした。
しかし、面談のなかで「数学には自信がありますか?」という質問には永田氏が大きく頷くといった「自己表現」をしたため、面談では合否保留とし、インターンシップ結果から判断することとなりました。インターンシップでは永田氏に対して、どういった目的のツール開発かを説明し、プログラムを一から製作するという課題を用意し取り組んでいただきました。
一方で、受け入れ先部署の従業員に対しては、障がい者職業センターから講師を招き、発達障がいに関する勉強会を行うなど、永田氏を受け入れるに際して必要な理解促進のための取り組みを行いました。
インターンシップにおいて、永田氏は与えられた課題を早々に仕上げるだけではなく、得意な別のプログラミング言語ならもっと良い提案ができるという発言もあり、インターンシップ終了時には永田氏の採用に迷いはありませんでした。
入社時の唯一の悩みは、「彼の能力を最大限に引き出すことができるかは受け入れ現場の我々にある」と、受け入れる立場としての責任と期待を研究開発部門のマネジャーは感じていました。

雇用に当たり取り組んだこと
永田氏を理解するための勉強会に加え、彼に必要な配慮を部署で理解し提供できる環境作りを行いました。
例えば、入社当初からコミュニケーションに不得意を感じていたため、新入社員研修は参加しない選択肢を用意しました。また、業務のなかでも、コミュニケーションをできるだけ取らない形で業務の依頼や指示ができるようにしたほか、他部署との交渉や、連絡窓口は別の担当が実施(間に他の社員を挟む)といった工夫を取り入れました。配属当時の上司や種子田氏などの部署メンバーは、質問に対して30分以上間が空くなど、時間がかかっても構わないので、考えていることを発言してもらうようにするなど、永田氏の特徴を否定せず、彼に合わせた配慮を行うことで、彼の強みが発揮できる環境を作っていきました。
正社員登用後には、評価面談を行うシートの記入については永田氏は文章の入力が不得意と感じているため、指導担当の種子田氏が代わりに記入し、永田氏と内容の整合後に上司に提出するようにしています。
また、上司との面談を定期的に実施し、職場での配慮や勤務上での困りごとの確認を行っています。永田氏が一人暮らしをしていた際は、健康面のフォローのため、産業医・臨床心理士・保健師とも定期的な面談を実施していました。今回、新型コロナの影響により自宅でのリモートワークを余儀なくされた結果、体調面で気になるところが見られたため現在は実家のある山口県に居を移し、健康面の管理についてはご家族からのサポートを受けながら遠隔地勤務をしてもらっています。

永田氏の雇用を通して得られたこと
永田氏の雇用を多くの方にご覧いただくためのドキュメンタリー映像を制作しました。社内にてこの映像を見た従業員を対象にアンケートを実施したところ、回答の多くが雇用を評価する内容でした。
『ドキュメンタリー動画満足度』
「お互いを理解し、その人その人に合ったコミュニケーションをするということが大切だと感じ、それは、健常者同士のチームのマネジメントと根本的には変わらないのだと感じました(管理職、マネジャー)」
「そのこだわりの強さが製品開発の一役を担っていることをこの動画で知りました(メンバー)」
「リコーの良いところが表現できている動画でした(メンバー)」
『障がい者の活躍推進について、イメージは変わりましたか?』
「個人の障がい有無、得手不得手に関係なくメンバーが最高のパフォーマンスを発揮するためのサポートができるようもっと努力しなければいけない、と思いました(管理職、マネジャー)」
「企業に勤めたり、チームで活躍することが可能だという認識がなかった」
映像:【採用】社員1日密着ドキュメンタリー “6年目研究 永田さん編”
職場では永田氏の受け入れをきっかけに障がいの有無に関係なく周囲が相互理解について意識するようになってきました。永田氏は文章や言葉で伝える時にたくさんのことを考えすぎてしまい、どれを伝えればいいのかが判断できない特徴があります。それは永田氏が日報を書く場面でも同様でした。そこで、伝える意思があることを「?」などの記号でも良いので書いてもらうようにすることで、永田氏の広い考えを周囲のメンバーに共有するようにしました。これはメンバーが多様な考え方について深く考えるようになったきっかけにもなりました。また、結果として永田氏もメンバーの方に少しずつ歩み寄りが感じられるようになりました。
今後の障がい者雇用についてですが、当社は「人」を尊重し、最大限に活かすための経営戦略としてダイバーシティ&インクルージョン推進に今後も取り組みます。多様な人材が能力をフルに発揮し、活躍する職場となり、多様な知識・経験・感性を 持った人が集まり、アイデアを創出することで、新たな付加価値・イノベーションを創出し、リコーとして企業価値の向上につなげていきます。
障がい者の活躍推進、女性活躍推進、シニア世代のキャリア支援、外国籍や多様な職歴・経験者への支援などなど、それぞれ方向性を決めて取り組みます。



同社の取り組みをお聞きして、「個人の特性に対する理解と配慮」を実施することで人材の戦力化や組織の成長が実現できるということを強く感じる取材でした。組織が大きくなるにつれて個人の特性に周囲が合わせていくことが難しい職場もあるため、全ての組織で導入できるかという問題がある一方で、こういった成功事例が存在することも事実です。
ご協力ありがとうございました。