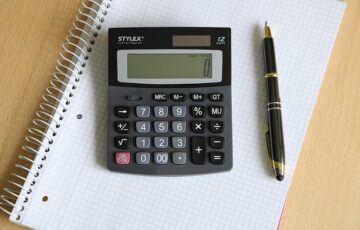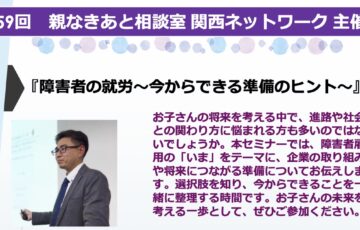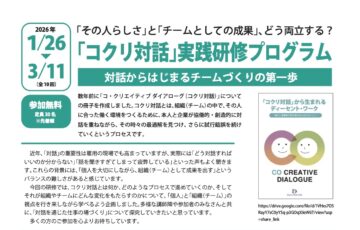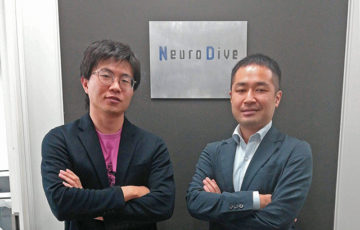【Q】
現在、障がい者を数名雇用しています。最近になりようやく精神障がい者の採用をすることができました。採用では数回の面接と職場では実習を行い、一緒に働く従業員の障がい者に対する理解を進めながら、取り組むことができたと思っています。
障がい者が職場で安心して業務に取り組んでもらうため、本人との定期的な面談を実施しています。それだけではなく、配属先の職場担当者とも面談を行い、担当者や一緒に働く従業員からのヒアリングも行っています。
先日、「業務ミスが連続で発生したのでどのように対処をすればいいか」と職場担当者から相談がありました。こちらからはミスしたところに関して指摘した方がいいのではと伝えたところ、「それで本人が自信を失い、休職してしまわないか心配だ」とのこと返答がありました。その後、部署では本人がミスをしてもまわりに影響が出にくい業務を担当してもらうように検討をしていると報告がありました。
障がい者が業務でミスしても本人が傷つかないように簡易な業務に変更することは本当の配慮と言えるのでしょうか。とはいえ、本人を傷つけてしまうかもしれないと考えてしまうのも理解ができます。
このような時、会社としてはどのような対応が必要だと考えますか。アドバイスがあれば教えてください。よろしくお願いします。
《住宅メーカー、従業員数約200名、人事担当》
【A】
障がい者雇用を進める中で「業務」の切り出しやマッチングに関する課題にほとんどの企業がぶつかります。今回は業務との適性やマッチングに加えて、本人へのミスの伝え方・アプローチ方法、配慮に関する考え方についてのご相談ですが、決して特殊な相談内容ではなく、同じように悩んでいる人事担当者・職場責任者も少なくありません。
①業務との適性・マッチング
法定雇用率の引き上げや多様性人材の活躍推進など、障がい者の雇用が進んでいる昨今、職場で働く障がい者の姿やメディアを通して障がい者の活躍を見聞きする機会が増えてきていると感じます。障がい者雇用に取り組む企業は様々な採用ルートを活用しながら、ミスマッチを減らす工夫を凝らしています。
最近は採用活動時に実習を取り入れ、職場で実際に働く様子を通して、「本人にある障がい特性の理解」「業務との適性を図る」「障がい者・職場双方の安心感の醸成」のもと、雇用後の定着を実現しようとする企業が増えてきました。
障がい者の中には、特性が要因となりできることの範囲が限定されたり、得意と苦手のギャップが大きいなどの特徴が見られる方には、なるべく適性や強みを活かした役割りに就いてもらうことが本人はもちろん、一緒に働く従業員にとっても、会社にとっても求める成果を生み出すことができると考えます。
実習などの業務との適性判断の機会を設けることに加え、障がいの特性由来の強みがどこにあるのかを本人の意見も交えて見出すことも必要だと考えます。
②ミスの伝え方・アプローチについて

社会では人とのコミュニケーションや情報の伝達においてハラスメントに注意を払うことが求められる時代になりました。上司と部下、先生と生徒といった上下関係もこの数十年で大きく変化したと感じます。
仕事に就いている誰もが多かれ少なかれ業務上でミスを経験していると思います。ミスしたことに気が付かない場合、本人に対して上司や周囲から伝える場面があります。昔と違って、ミスしたことに対して感情的な表現をすることも職場では徐々に見られなくなり、今は本人がミスしたことによるショックで落ち込まないように気を配って伝えるところが増えてきているのではないでしょうか。また、労働力が減少を続け、求人募集により苦労してようやく採用した人材ですから、気持ちよく働いてもらいたい・辞められてしまうと困ると考える上司も少なくないように感じます。
一方で、過失とはいえ業務上でミスをしたのであれば、本人にはそのことを理解してもらい、次に同様のミスをしないように注意を払う、より一層担当業務についての認識を深めてもらう、結果として本人の成長と評価につながるのだと考えます。障がい者の場合、特性が原因で発生したミスであれば、それらを補うための対処法(いわゆる合理的配慮)を本人と一緒に考え、実行するという考え方が重要になります。
③配慮に関する考え方

同社では障がいのある従業員が今後ミスをして自信を無くさないようにと考え「まわりに影響が出にくい業務への変更」を検討するとあります。おそらく、障がい者が勤務する職場では、本人のことを思っての判断なのですが、相談者である人事担当者はこのことについて疑問を呈していました。私もこの人事担当者と同様にこの考えが正解ではないと思います。
繰り返しとなりますが、企業による障がい者の雇用実数は年々増加しており、今後も引き上げられるであろう法定雇用率の達成や社会的な情勢を踏まえた障がい者の活躍の向上を考えると、これからも障がい者の活躍する姿が多くのところで見られることでしょう。
一方で障がい者を含めたマイノリティな方たちに対する偏見や差別もなかなか無くすことは難しいと感じます。職場では、悪意はなくとも障がい者と一緒に働くことに抵抗を感じたり、障がい者も仕事ができることをあまり信じていない人も一定数の割合で存在します。そういった方たちも含め職場には色々な考え方をする人が集まり、組織を形成しています。
厳しいことをお願いすることもあると思いますが、障がいがあっても会社から求められる役割や期待される仕事をこなし、成果を上げることで「障がい者も仕事ができる」ことを周囲に向けた証明になると考えます。
「まわりに影響が出にくい業務への変更」という判断が、障がい者本人が求める配慮の提供・周囲への協力の働きかけについて時間を掛けて考慮した上での答えなのか、今一度考えていただきたいと思います。