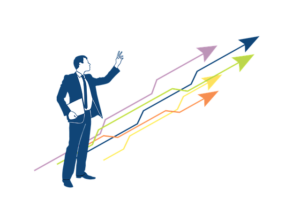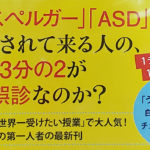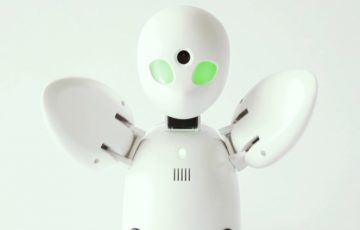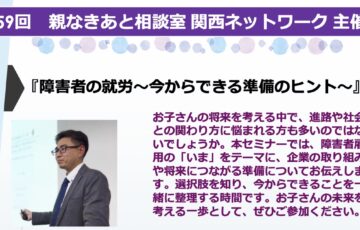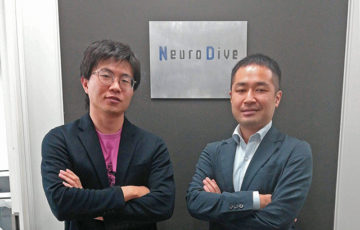米国でピザチェーンのドミノ・ピザに対し、視覚障がいの男性がウェブサイトやアプリのアクセシビリティが不十分でメニューを注文できなかったことがADA法(障がいをもつアメリカ人法)違反として訴えた裁判が起き、男性が勝訴しました。米国を中心に世界各国で報じられました。
Victory for disability advocates: Supreme Court won’t hear Domino’s Pizza accessibility case(USAトゥデイ)
Supreme Court allows blind man’s website lawsuit against Domino’s Pizza to proceed(フォックス)
Supreme Court hands victory to blind man who sued Domino’s over site accessibility(CNBC)
Supreme Court Rejects Domino’s on Blind Man’s Website Lawsuit(ブルームバーグ)
U.S. Supreme Court rejects Domino’s bid to avoid disabilities suit(ロイター)
米国最高裁が「企業ウェブ・アプリのアクセシビリティ対応は前提」と初の判断

「障がいをもつアメリカ人法」と訳されるADA法(Americans with Disabilities Act)は米国の障がい者政策の基本方針を示し、平等社会を目指す公民権法のひとつであり、1990年7月にブッシュ(父)政権下で成立しました。「障がいは個人ではなく社会の側にある」という社会モデルの思想があり、障がいを理由とした差別禁止、設備のアクセシビリティ改善、合理的配慮などが定められており、国連障がい者権利条約や日本を含む世界の障がい者法制にも影響を与えました。
しかし同法が成立した当時はインターネットが一般に開放されておらず(米国でインターネットが一般に開放されたのは1991年8月6日から)、ウェブやアプリのアクセシビリティに関する内容は同法にありませんでした。
その後、米国ではIT化が急速に進み、PCやスマートフォンは日常や仕事に欠かせないものになりました。そうした時代の流れと共に、障がい者もIT化に対応する意識が高まり、障がい者もアクセスできることを考えたウェブやアプリの開発がされるようになりました。しかしながらそれは公的機関では当然となったものの、民間企業ではばらつきが目立ちました。
米国在住の視覚障がいの男性ギレルモ・ローブレスさんは、PCを使う時にはスクリーンリーダーソフトウェア(視覚障がい者用PCに搭載される読み上げソフト)を利用しています。ピザと言えば米国ではハンバーガーやサンドイッチやホットドッグと並んで日常的な食べ物でリピート性の高い商品。しかしドミノ・ピザのウェブやアプリはスクリーンリーダーに対応しておらず、ローブレスさんが何度試みても結局できませんでした。ローブレスさんは、ドミノ・ピザが視覚障がい者にネット注文できるような対応を取らなかったとして、2016年9月に提訴しました。2019年6月には最高裁に上告されました。
この裁判は「ローブレス対ドミノ・ピザ訴訟(Robles v. Domino’s Pizza LLC, 913 F.3d 898)」という呼称で、ADA法に詳しい米国のサウスイーストADA センターのウェブサイトで経過が解説されています。
焦点となったのは、
- ADA法は一民間企業であるドミノ・ピザのウェブやアプリに適用されるか?
- ドミノ・ピザは、ウェブやアプリはADA法に従った公平な案内をしているか?
- 司法省は一民間企業であるドミノ・ピザの意思決定に介入すべきか?
米国のアクセシビリティ専門コンサルティング会社イコール・エントリーのトーマス・ローガン代表が日本で7月に行われた公益社団法人日本アドバタイザーズ協会Web広告研究会の月例セミナーで解説したことによると、ドミノ・ピザではウェブにアクセスすると獲得できる割引クーポンを用意していました。
しかし、このクーポンはスクリーンリーダーではアクセスできないので、ローブレスさんは安く購入できなかったのです。セールやクーポンなど金銭のやり取りに関連する情報は特にアクセシビリティを確保すべき情報だとして、ドミノ・ピザは訴訟を起こされたのです。
より細かく指摘すると、
- クーポンを取得する[ADD COUPON]ボタンをスクリーンリーダーでは操作できなかった
- ピザのトッピングを細かく指定する画面でも同様に、スクリーンリーダーでは適切に操作できないという問題もあった
- トッピングを細かくカスタマイズする画面もスクリーンリーダーでは操作できなかった
そのうえでローガン氏は、「ADA法は、事業内容や業種などを問わず適用されるので、米国では企業がADA法に基づいて提訴されるリスクがあります」と述べました。
米最高裁は10月7日、ローブレスさんの主張を認め、ADA法は民間企業のウェブやアプリも対象となり、ドミノ・ピザのウェブやアプリは視覚障がい者がアクセスできるように改善する必要があると判断しました。ドミノ・ピザは最高裁に対しウェブのアクセシビリティ改善を求める判断を避けるようにと主張していましたが、最高裁はこれを退けました。
近年、米国ではウェブやアプリのアクセシビリティに関する問題意識が高まるとともに訴訟が増えており、2018年には訴訟件数が約2200件と前年比でおよそ3倍の増加となっています(アクセシビリティ技術企業UsableNetの調査)。
ドミノ・ピザ訴訟の米最高裁の判決は、企業のウェブやアプリも障がい者のアクセシビリティ対応が前提とした初の判決となりました。今後のウェブやアプリの開発にも影響を与えそうです。
日本の人々の意識と視覚障がいなど障がい者の立場

ドミノ・ピザの訴訟、米国では大手のテレビ局・通信社・新聞の多くが報じていることでかなり注目度が高く、米国以外でも英国のロイターやBBCなどが報じています。今後、世界各国でウェブやアプリのアクセシビリティへの意識がますます高まりそうなニュースです。
日本人にはこうしたニュースには、「障がいを盾にしたクレーマー訴訟」「障がい者の言うことを全部聞いていると店が潰れる」「自分に合った店に行けばいいじゃん」「訴訟社会の弊害」「関係ない」という感想を持って終わる人も少なくないのではないでしょうか。
筆者が今年7月に、ドミノ・ピザ日本のウェブのアクセシビリティについて、SNS上で日本人の視覚障がい者数名に尋ねてみたところ、「代替テキストの標準化がされていない」との声がありました。
障がい者が使えるサービスにすることは、意識の高い企業だけが善意でやればいいことでしょうか。
企業のウェブやアプリが改善されれば、外出に困難を抱える視覚障がい者にとって便利に注文できてありがたい、というだけにとどまりません。
今日の就職活動や仕事においても、ネットを使って調べ物をするスキルは欠かせないもの。しかしウェブやアプリが視覚障がいに対応していなかったら?
視覚障がい者にとっては働くことに大きな支障が出てしまい雇用に影響するのではないでしょうか。
事実、日本の障害者雇用において、身体障がい者の就労は比較的進みましたが、身体障がいも様々で、視覚障がい、特に重度視覚障がい(全盲)となると話は別のようです。
厚生労働省による平成30年度障がい者の職業紹介状況で障がい者の就職件数を見ると、平成30年の身体障がい者全体の就職件数26841件のうち視覚障がい者は7.6%(2040件)、重度視覚障がい者になると4.3%(1167件)ときわめて低い割合になっています。
また視覚障がい者の職業別就職件数を見ると、「あはき業」と言われる、あんま・鍼・灸に従事する職業が視覚障がい者全体の39.3%(802件)、うち重度は647件(55.4%)で、この伝統的職業への大きな依存が依然として見られます(厚労省が日本盲人会連合に提供したデータより)。むしろ知的障がい者(就職件数22234件)や精神障がい者(同48040件)以上に理解が進みにくくなっているのでは、と言うのは言い過ぎでしょうか。
企業ウェブのアクセシビリティが不十分ならば、なるほど、企業としても「視覚障がい者にPCを使った仕事はさせられないな」になってしまうかもしれません。
しかし、障がい者が働くことが多い社会とそうでない社会では、どちらが生産性が高いでしょうか。障がい者に合ったサービスや情報が多い社会とそうでない社会では、どちらが経済効率が良いでしょうか。
障がい者が働いて経済力を持てば、家族の負担や社会保障費が減ることは間違いありませんし、それだけでなく、障がい者がお金を払ってより良いサービスや情報を受けてスキルアップや娯楽に使えるようになれます。まして、障がい者に合ったサービスや情報が多くなればなおさらです。そうしたサービスのメリットを受けられるのは障がい者や家族だけでなく、受け入れる企業も同様です。そして障がい者の貢献度がさらに高まります。
逆にそうでないと、障がい者に合った仕事やサービスや情報を探し回るために、あるいは彼らを援助するために、より多くの負担が本人や周囲(特に家族)にかかり、ますます彼らがお荷物扱いされてしまう、というふうに考えられないでしょうか。
全米ビジネス障がい者会議(NBDC)による2017年の調査では、全米の消費者の78%が「障がい者でも容易にアクセス可能であることを保障する取り組みを行っている企業の商品やサービスを購入したい」と回答しています。(以下のコラムにも書いたことです)
そして、そうした活動の先には当然のごとく企業のイメージアップというメリットがついてきます。